昨日は事前講習会、本日は初段技能検定を受けてきた。
藤枝市にある、静岡県武道館はもうかなりなれた場所となった。
日本武術太極拳連盟が定める、太極拳技能検定は
5級から3段までが試験を受験することで取得できるものとなっている。
4段、5段が新設となったが、いまのところ、一般受験者に関係はなさそうだ。
以前所属していた全日本柔拳連盟にも段位は存在したが、その基準などはあまりはっきりしたものではなかった。
それでも一応私の進度では4段取得、ということになるらしいが・・・
武術太極拳連盟の検定に話をもどそう。
通常、5級から一段階ずつ受験しないといけないのだが、私は5級から3級を飛び級受験し、2級、1級と今年の春までに取得し、今回の初段受験となった。
段は年に一回しか受験のチャンスがないので、受験者達はそれぞれ真剣そうであった。
受験科目は 筆記試験と簡化24式太極拳の全套路 である。
事前講習会では24式太極拳の実技が講習科目となる。
普段24式太極拳を練習の基本に据えていないわたしにとって、この講習会は求めているところ知る唯一のチャンス。
今回も滬杭武会の代表、伊東さんの奥さま、ハンドルネーム小彩さんから
数日前に一度24式をざっと見直してもらっていたので
ある程度は傾向がつかめていた。
私の班は三重県からきたO講師。温和だが、しっかり知識も技術もある講師で非常に勉強になった。
おそらく長拳や他の伝統拳も収められているのだろう。
私の動きをみて、午後の講習が始まる直前には「伝統拳か何かやってるでしょ!?」と
指摘され「とにかく検定では動きを見せつけずにさらっとやってください」とアドバイスされた。
連盟が目指す24式太極拳は、武術というよりも、「ゆるめる」という身体操作に主眼をおいている、
といったら怒られるかもしれないが、そのように感じる。
武術を学ぶ人間には物足りないかもしれないが、「そういう考え方もあるんだ」と知っておく分には
決しておかしなものではないと思った。
上歩して弓歩に移行するときに、すぐに上歩した足に体重を乗せに行かない
いわゆる「前引き」を極端に戒める点はある意味「虚実分明」の稽古ともいえる
私がいま学ぶ双辺太極拳でも弓歩の意識は後ろ足にある、といつも説明されるが、
それと共通点はあるように思われた。
そんなわけで前日講習は丸一日という長丁場であったが、無事終了
本日の試験は学科は「推掌」が含まれる動作を5つ書けというもので、どうやらここ数年は同じ問題のようだ。
普段中国語読みで教わっている人たちはそれなりに苦労されるようだが、
私は柔拳連盟時代からなぜか技法名は日本語読みで教わっていたので、それほど苦にならない
だが、昨日おさらいしていて「シャントンペイ」が「閃通臂」であることに気がついた
じつは今まで習ったものは「扇通背」となっていたため混乱したが(笑)
実技もおそらく問題ないと思う。
帰りは近頃知り合ったCさんと共に。車中ではずっと太極拳談義であった。
この話題はまた明日に・・・
藤枝市にある、静岡県武道館はもうかなりなれた場所となった。
日本武術太極拳連盟が定める、太極拳技能検定は
5級から3段までが試験を受験することで取得できるものとなっている。
4段、5段が新設となったが、いまのところ、一般受験者に関係はなさそうだ。
以前所属していた全日本柔拳連盟にも段位は存在したが、その基準などはあまりはっきりしたものではなかった。
それでも一応私の進度では4段取得、ということになるらしいが・・・
武術太極拳連盟の検定に話をもどそう。
通常、5級から一段階ずつ受験しないといけないのだが、私は5級から3級を飛び級受験し、2級、1級と今年の春までに取得し、今回の初段受験となった。
段は年に一回しか受験のチャンスがないので、受験者達はそれぞれ真剣そうであった。
受験科目は 筆記試験と簡化24式太極拳の全套路 である。
事前講習会では24式太極拳の実技が講習科目となる。
普段24式太極拳を練習の基本に据えていないわたしにとって、この講習会は求めているところ知る唯一のチャンス。
今回も滬杭武会の代表、伊東さんの奥さま、ハンドルネーム小彩さんから
数日前に一度24式をざっと見直してもらっていたので
ある程度は傾向がつかめていた。
私の班は三重県からきたO講師。温和だが、しっかり知識も技術もある講師で非常に勉強になった。
おそらく長拳や他の伝統拳も収められているのだろう。
私の動きをみて、午後の講習が始まる直前には「伝統拳か何かやってるでしょ!?」と
指摘され「とにかく検定では動きを見せつけずにさらっとやってください」とアドバイスされた。
連盟が目指す24式太極拳は、武術というよりも、「ゆるめる」という身体操作に主眼をおいている、
といったら怒られるかもしれないが、そのように感じる。
武術を学ぶ人間には物足りないかもしれないが、「そういう考え方もあるんだ」と知っておく分には
決しておかしなものではないと思った。
上歩して弓歩に移行するときに、すぐに上歩した足に体重を乗せに行かない
いわゆる「前引き」を極端に戒める点はある意味「虚実分明」の稽古ともいえる
私がいま学ぶ双辺太極拳でも弓歩の意識は後ろ足にある、といつも説明されるが、
それと共通点はあるように思われた。
そんなわけで前日講習は丸一日という長丁場であったが、無事終了
本日の試験は学科は「推掌」が含まれる動作を5つ書けというもので、どうやらここ数年は同じ問題のようだ。
普段中国語読みで教わっている人たちはそれなりに苦労されるようだが、
私は柔拳連盟時代からなぜか技法名は日本語読みで教わっていたので、それほど苦にならない
だが、昨日おさらいしていて「シャントンペイ」が「閃通臂」であることに気がついた
じつは今まで習ったものは「扇通背」となっていたため混乱したが(笑)
実技もおそらく問題ないと思う。
帰りは近頃知り合ったCさんと共に。車中ではずっと太極拳談義であった。
この話題はまた明日に・・・


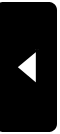

コメント